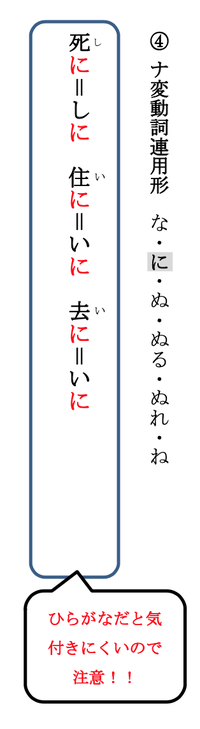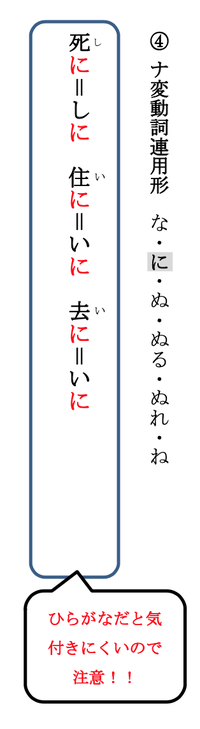【解答】
【解答】出題頻度1位!古典文法「に」の識別
「に」の識別は非常によくでるが、実はカンタンだ。
古典文法というとなんだか難しそうだが、
実は言葉なので例外が多く、それを丸暗記させられているから難しいのだ。
例外など問題にできないので無視すればいい。
法則どうりのものはかなり少ない!
この練習問題の短文を覚えてしまうのが近道!
【練習問題】次の傍線部の「に」は何か。
○a完了の助動詞 ○b断定の助動詞 ○c格助詞 ○d接続助詞 ○eナリ活用の形容動詞語尾
○fナ変動詞の語尾
1 七日
になりぬ。(船は)同じ港
にあり。
2 一夜のうちに塵(ちり)灰(はい)となり
にき。
3 神無月(かんなづき)晦日(つごもり)なる
に、紅葉散らで盛りなり。
4 黒き雲にはか
に出で来ぬ。
5 人の心すなおならねば、いつはりなき
にしもあらず。
6 (源氏は)所(ところ)狭(せ)き御身
にて、(見なれない山の景色を)めづらしう思されけり。
7 逃げて往
にけり。
解答 この7つは基本パターンなので必ず覚えよう。
1→両方とも ○c格助詞 (「に」と訳せる)
2→○a完了の助動詞 「にき・にけり・にたり」
3→○d接続助詞 (文と文をつなぐ)
4→○eナリ活用の形容動詞語尾 (「にはかなり」の連用形)
5→○b断定の助動詞 (に・あり→「で」と訳す。
「なきにしもあらず」は〈ないわけではない〉よく出るので覚えておこう。)
6→○b断定の助動詞 (「で」と訳せる。〈窮屈な御身分であって〉)
7→○fナ変動詞の語尾(「住ぬ」の連用形+けり)
【「に」のまとめ】
「に」の識別
「に」の識別問題はよくでる!センター試験でも出題頻度1位!読解でも大切。
大きく分けて「形で分かるもの」と「訳して判断するもの」がある。
まずは「形で分かるもの」から覚えよう。
◆形で分かるもの
① 接続助詞 (文と文をつなぐ。接続詞みたいなもの。意味は順接か逆接。)
文 に、 文
例 寄りて見るに、竹の中光りたり。〈近寄ると、竹の中が光っていた。〉
② 完了の助動詞「ぬ」連用形 (な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね)
動詞+にき(にし・にしか)・にけり・にたり・にけむ
〈・・した・しまった〉
※「にし」の「し」は過去の助動詞「き」の連体形。「にしか」の「しか」は已然形。
例 雨降りにき。〈雨が降った。〉 雨降りにし時、〈雨が降った時、〉
雨降りにしかど(ども)〈雨が降ったけれども
③ 形容動詞ナリ活用 連用形 (なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)
(いと)・・(か・がち・ら・れ・げ・ろ)に
「たいへん・・・だ」と訳せるもの!※「形容動詞」は状態を表す言葉だから
むべに→「宜(むべ)なり」(形容動詞)の連用形〈もっともだ・当然だ〉
例 なめげに〈無礼に〉まめやかに〈まじめに〉あながちに 〈強引に〉
④ ナ変動詞連用形 な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね
死(し)に=しに 住(い)に=いに 去(い)に=いに
※ひらがなだと気付きにくいので注意!!
⑤ 断定の助動詞「なり」の連用形 〈・・であろうか〉
(なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)
重要!!
断定の助動詞「なり」の連用形 〈・・であろうか〉
(なら・なり/に・なり・なる・なれ・なれ)
ぞ・なむ・や・か・こそ・し(も)など
↓
に や (あら む)←省略されるので注意!
↑ ↑助動詞 む・らむ・けむ・ず など
ラ変(あり・侍り・候ふ・おはす・おはします)
よくある形 (これらの「に」は断定)
・・・にや
・・・にこそ
・・・になむ
・・・にやあらむ
・・・にやありけむ
・・・にこそあらめ
・無きにしもあらず
〈ないわけではない=少しはある〉
・・・にやおはせむ
・・・にやおはしますらむ
・・・にや侍る
※クリックすると大きくなるよ